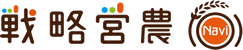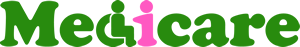SFAとはSales Force Automation の略称で、日本語で営業支援システムと呼ばれることもあります。
SFAとは、日々の活動記録やスケジュールを登録、顧客情報の一元管理を行うことで業務の効率化、営業力強化を支援するツールです。
営業活動の効率化だけではなく、顧客ひとりひとりに合わせた対応で顧客満足度の向上を支援します。
本記事ではSFA選びで大事な6点のポイントについてご紹介します。
SFAとは、日々の活動記録やスケジュールを登録、顧客情報の一元管理を行うことで業務の効率化、営業力強化を支援するツールです。
営業活動の効率化だけではなく、顧客ひとりひとりに合わせた対応で顧客満足度の向上を支援します。
本記事ではSFA選びで大事な6点のポイントについてご紹介します。
まずSFAの基本的な機能についてご紹介します。
・案件管理機能
商談ごとのステータス(見込み、提案、クロージングなど)を可視化することが可能です。
見積書や提案書を添付することも可能で、活動の履歴と共にどのような書類作成、共有したのかを管理することも可能です。
・営業活動の記録・管理
営業担当者が行った活動の記録(訪問、架電、メールなど)の記録を行うことで、顧客にどのような対応を行ってきたのかといった活動の振り返りが容易になります。
またリアルタイムで活動が記録されるため、ステータスに合わせた活動に対するアドバイスを行うことも可能です。
スマートフォン等のモバイル端末から入力が可能で、外出先からデータ確認、共有、記録も可能な製品もあります。
・予実管理、売上予測
受注見込み額や角度に基づいた売上予測、営業目標に対する達成状況の可視化など集計、管理が行えます。
目標に対する進捗を可視化することで、目標達成のためにどのような活動を行う必要があるのか確認できます。
・顧客管理機能(CRM)
顧客情報(企業名、担当者、業種、規模など)の情報を管理できます。
過去の商談履歴や問合せの履歴など顧客に関わる情報を一元管理できます。
その他、ご紹介した機能以外にもにも様々な機能がございます。
・案件管理機能
商談ごとのステータス(見込み、提案、クロージングなど)を可視化することが可能です。
見積書や提案書を添付することも可能で、活動の履歴と共にどのような書類作成、共有したのかを管理することも可能です。
・営業活動の記録・管理
営業担当者が行った活動の記録(訪問、架電、メールなど)の記録を行うことで、顧客にどのような対応を行ってきたのかといった活動の振り返りが容易になります。
またリアルタイムで活動が記録されるため、ステータスに合わせた活動に対するアドバイスを行うことも可能です。
スマートフォン等のモバイル端末から入力が可能で、外出先からデータ確認、共有、記録も可能な製品もあります。
・予実管理、売上予測
受注見込み額や角度に基づいた売上予測、営業目標に対する達成状況の可視化など集計、管理が行えます。
目標に対する進捗を可視化することで、目標達成のためにどのような活動を行う必要があるのか確認できます。
・顧客管理機能(CRM)
顧客情報(企業名、担当者、業種、規模など)の情報を管理できます。
過去の商談履歴や問合せの履歴など顧客に関わる情報を一元管理できます。
その他、ご紹介した機能以外にもにも様々な機能がございます。
SFAの選び方

それではSFAを選ぶために大切な6点のポイントについてご紹介します。
1.導入の目的を明確にする
まず導入目的を明確にすることが大切です。
SFAは日々のデータを蓄積することが重要です。
目的が曖昧なまま入力だけを続けると「何のためにやっているのか」と感じ、次第に運用が形骸化してしまいます。
データを入力することで、蓄積されたデータが今後どのように役に立つのか、どんな成果につながるのかをきちんと明確にすることが大切です。
2.自社に必要な機能を吟味する
SFAを導入するにあたって、自社に必要な機能を吟味することも大切です。
先ほどSFAの基本的な機能について簡単にご紹介しましたが、SFAによって強みは様々です。
例えば基幹システムやMAツールと連携できるものなど連携機能に優れているもの、地図機能が優れているもの、名刺読取機能があるものなどSFAごとに優れている機能、特長があります。
自社に必要な機能を吟味し、自社のニーズに合った製品を選ぶことが大切です。
3.費用対効果を見極める
SFAには様々な機能があり、製品によってかかる費用は異なります。
例えば機能は充実しているが比較的高価なSFA、または機能が限定されており比較的安価なSFA、など様々なSFAがあります。
機能がありすぎて自社には必要のない機能が多いといった意見もあれば、安価だと思い導入したものの、機能が不足しており効果的に使うことができていない、といった場合もあります。
費用と機能のバランスを見極め、自社に合った投資判断を行うことが大切です。
4.現場社員が使いやすいツールか
SFAは日々データを入力する現場担当者にとって使いやすいツールであることが大切です。
毎日データを入力するため、必要最低限の入力・操作で完了できるツールや、直感的にわかりやすいツールを選ぶと良いでしょう。
例えばデータ入力時、テキストボックスの記述が多かったり、必要のない項目を非表示にできないと手間に感じてしまいます。
画面項目を設定する際に、チェックボックスやプルダウンメニューといった項目を自由に設定、非表示にできるもの選ぶなど、手間を減らせる仕組みがあるか確認しましょう。
5.他のシステムと連携できるか
システム連携が可能かどうかもSFAを選ぶ上で重要です。
例えば基幹システムと連携できなければ、二重入力が発生し、効率化が妨げられます。
SFAで情報を一元管理するにあたって、他システムとの連携は必ず確認しましょう。
6.サポートが充実しているか
サポートが充実しているかも確認する必要があります。
SFAを提供しているベンダーの中には、チャットやメールでのお問合せのみ受け付けており、お問合せからレスポンスまで1~2日ラグがあるようなサポート体制になっていることがあります。
対して電話で直接お問合せができる、コールセンターがある製品や、導入後に操作方法や活用方法に不便な点がないか確認する導入支援を行っている企業もあります。
SFAを選ぶ上で自社にはどのようなサポートが必要なのか、水準を見極めて選ぶことが大切です。
1.導入の目的を明確にする
まず導入目的を明確にすることが大切です。
SFAは日々のデータを蓄積することが重要です。
目的が曖昧なまま入力だけを続けると「何のためにやっているのか」と感じ、次第に運用が形骸化してしまいます。
データを入力することで、蓄積されたデータが今後どのように役に立つのか、どんな成果につながるのかをきちんと明確にすることが大切です。
2.自社に必要な機能を吟味する
SFAを導入するにあたって、自社に必要な機能を吟味することも大切です。
先ほどSFAの基本的な機能について簡単にご紹介しましたが、SFAによって強みは様々です。
例えば基幹システムやMAツールと連携できるものなど連携機能に優れているもの、地図機能が優れているもの、名刺読取機能があるものなどSFAごとに優れている機能、特長があります。
自社に必要な機能を吟味し、自社のニーズに合った製品を選ぶことが大切です。
3.費用対効果を見極める
SFAには様々な機能があり、製品によってかかる費用は異なります。
例えば機能は充実しているが比較的高価なSFA、または機能が限定されており比較的安価なSFA、など様々なSFAがあります。
機能がありすぎて自社には必要のない機能が多いといった意見もあれば、安価だと思い導入したものの、機能が不足しており効果的に使うことができていない、といった場合もあります。
費用と機能のバランスを見極め、自社に合った投資判断を行うことが大切です。
4.現場社員が使いやすいツールか
SFAは日々データを入力する現場担当者にとって使いやすいツールであることが大切です。
毎日データを入力するため、必要最低限の入力・操作で完了できるツールや、直感的にわかりやすいツールを選ぶと良いでしょう。
例えばデータ入力時、テキストボックスの記述が多かったり、必要のない項目を非表示にできないと手間に感じてしまいます。
画面項目を設定する際に、チェックボックスやプルダウンメニューといった項目を自由に設定、非表示にできるもの選ぶなど、手間を減らせる仕組みがあるか確認しましょう。
5.他のシステムと連携できるか
システム連携が可能かどうかもSFAを選ぶ上で重要です。
例えば基幹システムと連携できなければ、二重入力が発生し、効率化が妨げられます。
SFAで情報を一元管理するにあたって、他システムとの連携は必ず確認しましょう。
6.サポートが充実しているか
サポートが充実しているかも確認する必要があります。
SFAを提供しているベンダーの中には、チャットやメールでのお問合せのみ受け付けており、お問合せからレスポンスまで1~2日ラグがあるようなサポート体制になっていることがあります。
対して電話で直接お問合せができる、コールセンターがある製品や、導入後に操作方法や活用方法に不便な点がないか確認する導入支援を行っている企業もあります。
SFAを選ぶ上で自社にはどのようなサポートが必要なのか、水準を見極めて選ぶことが大切です。
まとめ
SFAを選ぶ際は、
1.導入目的
2.必要な機能
3.費用対効果
4.現場での使いやすさ
5.他システムとの連携
6.サポート体制
これらのポイントを確認することが成功のカギとなります。
今回ご紹介した点についてご確認していただけたら幸いです。
1.導入目的
2.必要な機能
3.費用対効果
4.現場での使いやすさ
5.他システムとの連携
6.サポート体制
これらのポイントを確認することが成功のカギとなります。
今回ご紹介した点についてご確認していただけたら幸いです。