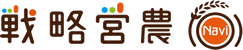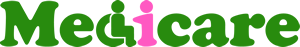SFAとは?営業支援ツールの基本を理解する
営業活動を効率化するためのツールとして「SFA」がよく挙げられますが、
「SFA」という言葉を耳にしたことはあるがあまり詳しく知らない、そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回のコラムではSFAの基礎から導入前に知りたいメリットやポイントについて簡単にご紹介していきます。
今回のコラムではSFAの基礎から導入前に知りたいメリットやポイントについて簡単にご紹介していきます。
SFA(営業支援ツール)の定義と役割
SFAとはSales Froce Automationの略称で、日本語では「営業支援ツール」と呼ばれています。
SFAとはその名の通り、営業プロセスを自動化・効率化するためのツールです。
例えば案件の進捗をリアルタイムで管理したり、タスクを自動化し業務効率化を実現、売上予測といった戦略立案にも活用いただけるような仕組みです。
SFAとはその名の通り、営業プロセスを自動化・効率化するためのツールです。
例えば案件の進捗をリアルタイムで管理したり、タスクを自動化し業務効率化を実現、売上予測といった戦略立案にも活用いただけるような仕組みです。
営業活動におけるSFA(営業支援ツール)の重要性

BtoB営業では「組織的に検討するため、購入までに時間がかかる」という特徴があります。
そのため、ファーストコンタクトから購入に至るまで、定期的に営業活動を続けなければなりません。
このようにBtoBにおける営業プロセスは、複雑で長期的な営業プロセスが一般的です。
SFAは、そのような複雑で管理しずらい営業活動を効果的に管理することで、業務の効率化、売上増加を目指すために必要不可欠なツールです。
例えば、SFAを導入することで、以下のような利点が得られます。
・商談の進捗が見える化されることで、受注率が高いプロセスを標準化できる
・情報の一元管理により事業部をまたいだ情報共有が簡単にできる
・顧客の情報を蓄積するため、より顧客に寄り添った提案が可能になる
このように、SFAを活用することが売り上げの増加、成約率の上昇や顧客満足度の向上につながります。
そのため、ファーストコンタクトから購入に至るまで、定期的に営業活動を続けなければなりません。
このようにBtoBにおける営業プロセスは、複雑で長期的な営業プロセスが一般的です。
SFAは、そのような複雑で管理しずらい営業活動を効果的に管理することで、業務の効率化、売上増加を目指すために必要不可欠なツールです。
例えば、SFAを導入することで、以下のような利点が得られます。
・商談の進捗が見える化されることで、受注率が高いプロセスを標準化できる
・情報の一元管理により事業部をまたいだ情報共有が簡単にできる
・顧客の情報を蓄積するため、より顧客に寄り添った提案が可能になる
このように、SFAを活用することが売り上げの増加、成約率の上昇や顧客満足度の向上につながります。
SFA(営業支援ツール)とCRMの違いを解説
SFAについて情報収集をしていると、CRMという言葉を耳にすることがあるかもしれません。
CRMとはCustomer Relationship Managementの略称で、日本語では「顧客関係管理」と呼ばれています。
主に顧客の情報を管理するためのツールのことを指し、顧客との関係を構築し顧客満足度の向上を実現するために用いられます。
SFAでは商談から受注までの活動を管理するのに対し、CRMは顧客情報管理や受注後の顧客との関係性構築などに活用されています。
最近はSFAとCRM、両方の機能を兼ね備えたツールが主流になっており、受注前から受注後のアフターフォローまで対応しているツールも多く存在します。
CRMとはCustomer Relationship Managementの略称で、日本語では「顧客関係管理」と呼ばれています。
主に顧客の情報を管理するためのツールのことを指し、顧客との関係を構築し顧客満足度の向上を実現するために用いられます。
SFAでは商談から受注までの活動を管理するのに対し、CRMは顧客情報管理や受注後の顧客との関係性構築などに活用されています。
最近はSFAとCRM、両方の機能を兼ね備えたツールが主流になっており、受注前から受注後のアフターフォローまで対応しているツールも多く存在します。
SFA(営業支援ツール)導入の目的とメリット

SFA導入の目的は企業によってさまざまですが、「営業効率の向上」や「顧客満足度の向上」、「営業チームの標準化」などが挙げられます。
しかしSFAを用いることで情報が一元管理され、顧客に紐づいた情報を一覧で見ることができるようになります。
担当者が休みの場合でも、SFAを参照することで別の担当者でもすぐに対応可能になり、また過去の活動履歴も確認できるため、担当者の引継ぎが容易になります。
他にも、紙ではなくクラウドでの管理になるため活動日報などを外出先から記入・提出できるようになり、隙間時間の活用や、わざわざ紙で提出するために帰社しなければならなかった、というような時間も削減できます。
このようにSFAを活用することで業務の効率化、時間の削減を実現します。
顧客にまつわるデータがすべてSFAに蓄積されているため、営業担当者以外の、保守担当者や窓口担当者など部署が異なる担当者が入手した情報も管理されます。
そのため顧客の需要を漏れなく把握できるようになり、より顧客が望む提案を新たに行うなど顧客満足度の向上を手助けします。
他にも管理者が進捗を管理できておらず、提案機会を損失してしまっていた、そんなこともあったかもしれません。
SFAで商談プロセスを管理することでアプローチから受注までの一連の流れが見える化され、どこに問題があったのか、わかりやすくなります。
成約率が良い営業と、なかなか成約に繋がらない営業のアプローチを見比べた時に、例えば「提案の仕方が良くない」「訪問時期が遅い」など改善策が見つかります。
成約率が高い営業手法、プロセスを各営業に展開することで、組織全体の営業力の底上げができ、営業チーム全体の成果の向上を見込めます。
・営業効率の向上と時間削減
例えば、これまで各担当者が紙やExcelで日々の活動や日報を管理しており、属人化されている場合、顧客からの問い合わせ対応や引継ぎに時間や手間がかかっていました。しかしSFAを用いることで情報が一元管理され、顧客に紐づいた情報を一覧で見ることができるようになります。
担当者が休みの場合でも、SFAを参照することで別の担当者でもすぐに対応可能になり、また過去の活動履歴も確認できるため、担当者の引継ぎが容易になります。
他にも、紙ではなくクラウドでの管理になるため活動日報などを外出先から記入・提出できるようになり、隙間時間の活用や、わざわざ紙で提出するために帰社しなければならなかった、というような時間も削減できます。
このようにSFAを活用することで業務の効率化、時間の削減を実現します。
・データ蓄積と顧客管理の強化
顧客に紐づいた情報を簡単に確認できるようになることで、問い合わせ対応や引継ぎが簡単になる、とお伝えしましたが情報一元化のメリットはそれだけではありません。顧客にまつわるデータがすべてSFAに蓄積されているため、営業担当者以外の、保守担当者や窓口担当者など部署が異なる担当者が入手した情報も管理されます。
そのため顧客の需要を漏れなく把握できるようになり、より顧客が望む提案を新たに行うなど顧客満足度の向上を手助けします。
・営業チームの成果を向上させる
商談プロセスの一連の流れを見える化していなかった場合、失注時にどこが問題があったのかなど課題発見に時間がかかります。他にも管理者が進捗を管理できておらず、提案機会を損失してしまっていた、そんなこともあったかもしれません。
SFAで商談プロセスを管理することでアプローチから受注までの一連の流れが見える化され、どこに問題があったのか、わかりやすくなります。
成約率が良い営業と、なかなか成約に繋がらない営業のアプローチを見比べた時に、例えば「提案の仕方が良くない」「訪問時期が遅い」など改善策が見つかります。
成約率が高い営業手法、プロセスを各営業に展開することで、組織全体の営業力の底上げができ、営業チーム全体の成果の向上を見込めます。
SFA(営業支援ツール)導入の成功事例
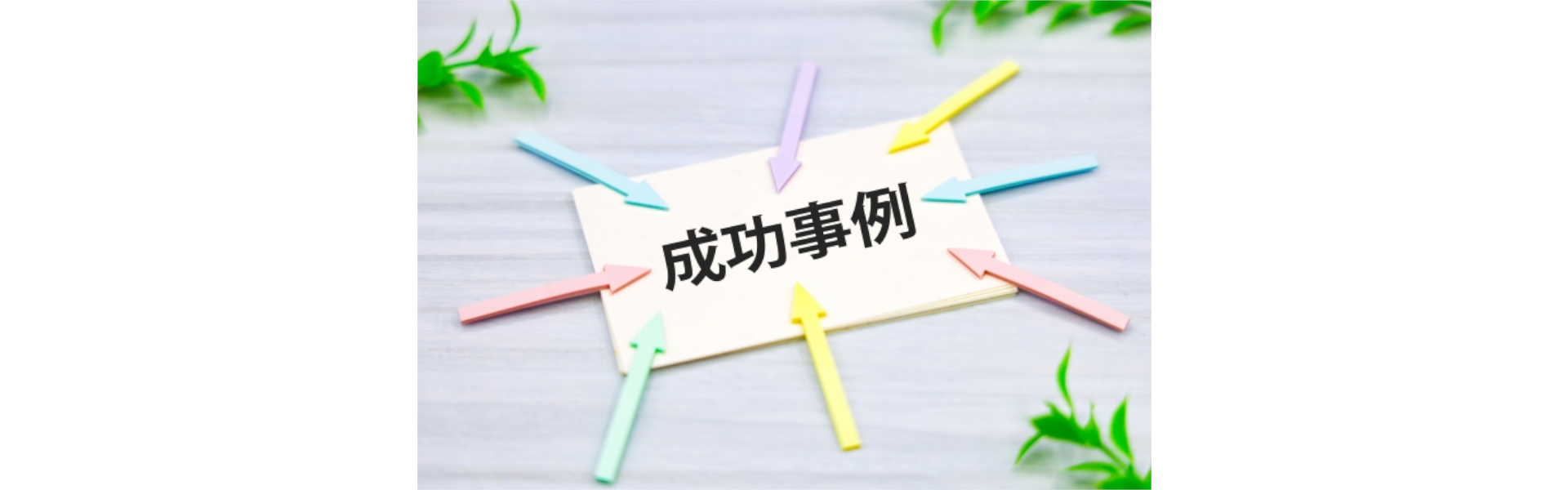
それではここからは、SFAの導入事例についてご紹介していきましょう。
弊社が取り扱っているSFA/CRM「戦略箱ADVANCED」のご導入事例です。
導入事例①
創業以来50年にわたり業務用パンの製造販売を手掛けている老舗パンメーカーの「株式会社エースベーキング」様は、 SFAの導入によって無駄の多い紙ベースでの管理から脱却、スムーズな情報共有やタイムリーなマネジメントが可能になり、業務効率化を実現しました。
利用ユーザ:20名
導入目的:各事業部での営業情報、商品情報、顧客情報の共有
活用方法:情報の共有・展開
導入効果:成功事例や他事業部の取り組みの社内展開が可能になり、部下への指導・アドバイスを場所や時間に関わらず行えるようになったことで、営業活動の効率化ができるようになりました。
弊社が取り扱っているSFA/CRM「戦略箱ADVANCED」のご導入事例です。
・SFA(営業支援ツール)導入事例紹介
導入事例①
創業以来50年にわたり業務用パンの製造販売を手掛けている老舗パンメーカーの「株式会社エースベーキング」様は、 SFAの導入によって無駄の多い紙ベースでの管理から脱却、スムーズな情報共有やタイムリーなマネジメントが可能になり、業務効率化を実現しました。
利用ユーザ:20名
導入目的:各事業部での営業情報、商品情報、顧客情報の共有
活用方法:情報の共有・展開
導入効果:成功事例や他事業部の取り組みの社内展開が可能になり、部下への指導・アドバイスを場所や時間に関わらず行えるようになったことで、営業活動の効率化ができるようになりました。
導入事例②
岐阜、愛知、東京、群馬など全国に支社を持ち、フリーマガジンの発行を行っている総合広告会社「株式会社中広」様は、 SFAの導入によって、タイムラグが発生していた紙による管理からの脱却、業務の効率化や蓄積したデータの戦略立案への活用を実現しています。
利用ユーザ:450名
導入目的:営業部門の受注・売上・仕入れ管理のシステム化
活用方法:売上情報の管理、顧客情報の共有・蓄積
導入効果:売上情報を個人単位、支社単位など容易に管理できるようになり、顧客情報を元にターゲット先を選定するなど、業務効率化・蓄積したデータの活用を実現しています。
成功するためのポイント
SFAの導入を成功させるために必要なことは「SFA導入の目的を明確にする」「サポート体制が充実したベンダーを選ぶ」「自社に最適なシステムを選ぶ」ことが大切です。
・SFA導入の目的を明確にする
SFA導入の目的を管理部門だけではなく、現場の担当者まで浸透させる必要があります。例えばこれまでは紙での管理が多かった場合、PCやスマホから日々の活動を報告することに、慣れるまでデータ入力を負担に感じるかもしれません。
SFAはすぐに効果が表れるものではなく、日々データを蓄積することで、活用できるようになっていきます。
まだ効果を感じられない状態で「SFA導入の目的を理解しないまま、ただ入力しているだけ」といった状態が続くと、データ入力を負担に感じて次第にデータが入力されなくなってしまうかもしれません。
そんなことにならないためにも、現場の担当者まで、なぜSFAを導入するのか、SFAを活用することで得られる効果について周知してください。
・サポート体制が充実したベンダーを選ぶ
SFA導入直後は、操作方法がわからなかったり、こういうことがしたい、といった要望が出てくると思います。そんなときに、確認できるマニュアルがあるのか、または電話で回答してもらえるのか、はたまたメールのみの対応なのか、サポート体制は製品によって様々です。
サポートの内容によっては有償対応になったり、お問合せのたびに料金が発生するものもあります。
運用していく上で、自社に寄り添った対応をしてくれるかどうかもSFA導入成功の鍵になってきます。
・自社のニーズに応じたシステム選定
SFAを導入する際に、きちんと自社のニーズに応じたシステムを選定・導入することが大切です。例えば「基幹システムと自動連携して、入力の手間を削減したい」ならば、連携に優れた製品を選ぶと良いでしょう。
他にも「SFAを導入しても自社だけで運用・定着できるか不安」ならば、サポートが充実した製品、 「受注前の案件管理だけではなく受注後の顧客接点まで管理したい」ならば、SFAだけではなく、CRM機能も兼ね備えた製品が良いでしょう。
このようにSFAは製品によって様々な特徴があります。
SFA導入によって期待している効果を得るためには、自社の目的に合わせてシステムを選定・導入をよく吟味されると良いでしょう。
SFA(営業支援ツール)導入前に知っておきたいデメリット

SFAで得られるメリットもある反面、SFA導入によって出てくるデメリットについてもご紹介します。
基本的に機能が充実しているものほど高額になり、安価なものもありますが、パッケージではなく、自社でアプリを作成する必要があったり、日々の管理・保守が大変といったように時間コストがかかります。
自社の課題を洗い出し、必要な機能を絞ったり自社の環境確認してどの製品が自社に合っているのか、よく確認する必要があります。
SFAも同様に、SFAに慣れるまで入力に時間がかります。
少しでも入力負担を減らすためには、入力項目を必要なものだけに絞ることが大切です。
自社の運用に合わせたカスタマイズや設定ができるようなツールを選ぶことで、入力負担・時間の減少が可能です。
・導入コストと運用負担
SFAの導入にはどうしてもコストがかかってしまいます。基本的に機能が充実しているものほど高額になり、安価なものもありますが、パッケージではなく、自社でアプリを作成する必要があったり、日々の管理・保守が大変といったように時間コストがかかります。
自社の課題を洗い出し、必要な機能を絞ったり自社の環境確認してどの製品が自社に合っているのか、よく確認する必要があります。
・入力に時間がかかる
何事も慣れるまでは少し時間がかかってしまいます。SFAも同様に、SFAに慣れるまで入力に時間がかります。
少しでも入力負担を減らすためには、入力項目を必要なものだけに絞ることが大切です。
自社の運用に合わせたカスタマイズや設定ができるようなツールを選ぶことで、入力負担・時間の減少が可能です。
営業支援におけるSFAの機能
SFAの基本的な機能についてご紹介していきます。
SFAの顧客管理では顧客の氏名といった基本的な情報から、過去の自社担当者履歴や提案履歴、問合せ履歴など顧客に関連する情報を一元管理します。
現在取引がある顧客以外にも、今後取引していきたい見込み顧客の情報も管理可能です。
SFAの商談管理では、商談の発掘から、アプローチ、クローズまでのプロセスの進捗状況を共有したり、商談と日々の活動記録を紐づけて管理できます。
SFAによって機能が異なり、扱う商材や部門によって管理項目やプロセスを自由に設定できたり、定期的な商談を自動作成できる機能など様々です。
商談と日々の活動が紐づいて管理できるため、欲しい情報を素早く確認でき、情報共有の時間短縮や、部内の定期MTGでの活用など営業の効率化を支援します。
顧客とのアポイントや会議の予定など、担当者の日々のタスク、スケジュールを可視化し、管理します。
日々の業務を見える化することで、タスク漏れを防ぎます。
こういったスケジュール管理はSFAではなく全社的に他のツールで担っている、といった場合もあります。
そういった場合には二重入力を避けるため、他ツールと連携が可能な製品を選択されると良いでしょう。
日報や週報、1回の訪問で1報告など、報告の間隔や方法は異なりますが営業にとって日報は欠かせないものです。
SFAを利用することで顧客と商談に情報が紐づき、必要な情報が漏れなく管理されます。
情報が一元管理されるので、人事異動の際や担当者がお休みといった場合にもすぐに情報を確認できるようになり、情報共有の負担が削減します。
週次、月次、年次といった時間軸での管理や、担当者別、チーム別など様々な単位で管理します。
自社の売り上げの傾向をつかんだり、次に攻めるべきターゲットを見極めるなど営業戦略に活用できます。
顧客管理機能
SFAの顧客管理では顧客の氏名といった基本的な情報から、過去の自社担当者履歴や提案履歴、問合せ履歴など顧客に関連する情報を一元管理します。
現在取引がある顧客以外にも、今後取引していきたい見込み顧客の情報も管理可能です。
商談管理
SFAの商談管理では、商談の発掘から、アプローチ、クローズまでのプロセスの進捗状況を共有したり、商談と日々の活動記録を紐づけて管理できます。
SFAによって機能が異なり、扱う商材や部門によって管理項目やプロセスを自由に設定できたり、定期的な商談を自動作成できる機能など様々です。
商談と日々の活動が紐づいて管理できるため、欲しい情報を素早く確認でき、情報共有の時間短縮や、部内の定期MTGでの活用など営業の効率化を支援します。
スケジュール管理
顧客とのアポイントや会議の予定など、担当者の日々のタスク、スケジュールを可視化し、管理します。
日々の業務を見える化することで、タスク漏れを防ぎます。
こういったスケジュール管理はSFAではなく全社的に他のツールで担っている、といった場合もあります。
そういった場合には二重入力を避けるため、他ツールと連携が可能な製品を選択されると良いでしょう。
日報管理
日報や週報、1回の訪問で1報告など、報告の間隔や方法は異なりますが営業にとって日報は欠かせないものです。
SFAを利用することで顧客と商談に情報が紐づき、必要な情報が漏れなく管理されます。
情報が一元管理されるので、人事異動の際や担当者がお休みといった場合にもすぐに情報を確認できるようになり、情報共有の負担が削減します。
売上管理
週次、月次、年次といった時間軸での管理や、担当者別、チーム別など様々な単位で管理します。
自社の売り上げの傾向をつかんだり、次に攻めるべきターゲットを見極めるなど営業戦略に活用できます。
SFA(営業支援ツール)の運用と教育体制

SFAをただ導入するだけでは定着しません。
きちんと教育体制を整えたり、導入の目的を明確化することが大切です。
社員教育の重要性
新しいシステムを導入する場合、操作方法や活用方法などわからないことが出てくると思います。入力をする現場の担当者が操作方法をわからなければ、データが入力・蓄積されていきません。
そうならないためにも、運用開始前に操作方法を丁寧に教育することが大切です。
導入の目的
導入のポイントの際に、導入の目的を明確化することが大切だと述べました。導入直後は新しい方法に慣れず時間がかかってしまい、なかなかデータが入力されないこともあるかもしれません。
定着するためには目的をきちんと現場担当者まで浸透させ、なぜSFAを導入したのか理解しながら使ってもらうことが定着につながります。
またSFAを導入後、「SFAの使用」が目的にならないように注意することが大切です。
SFAを導入したとしても、SFAに入力することが目的となってしまい、データを活用できていなかったとします。
そんな場合はSFAにデータを入力・蓄積することで得られる効果を実感できないかもしれません。
SFAにデータを入力することで、営業活動を可視化します。
そこで浮かび上がってきた問題点の改善に取り組むなどPDCAを回すことで入力者自身も効果を実感、データを活用できるような体制で運用することも大切です。
定着化のための運用体制の構築
SFAを定着するためにも事前にルール決めをすることが大切です。例えば、株式会社か(株)にするのかなど、顧客情報の入力方法を定義することが必要です。
そうすることで入力したデータにばらつきが出ず、情報の活用や検索性が上がります。
他にも自社に合わせた操作マニュアルを事前に用意する、SFAの管理者を決める、などある程度決めておくことで定着しやすくなり、長く運用いただけます。
もし自社だけでは難しい場合は、運用時のルール定義を一緒に考えてくれるベンダーや操作方法の勉強会など導入補助を行っているSFAベンダーを選ぶことも考えてはいかがでしょうか。
SFA(営業支援ツール)導入後の効果測定

SFA導入後の効果を可視化することで、データ入力の意欲に繋がります。
成果を可視化する
例えば、今まで隔週である営業会議に使う資料を作るのに2時間かかっていたとします。しかしSFAに日々データを蓄積しており、資料作成の時間が30分になり、手間と時間が削減できていることがわかれば、日々SFAにデータを蓄積することの重要性がわかります。
他にもSFAに商談のプロセスや進捗、活動履歴が蓄積されたことによって、「勝ちパターン」と「負けパターン」が見える化されるかもしれません。
今まで成約率が良くなかった営業パーソンに「勝ちパターン」を当てはめることで成約率が増加するかもしれません。
このようなSFA導入前と導入後の成果を可視化することで、SFA導入の意義が見えてきます。
反対になかなか効果が見られない、そんな場合もあるかもしれません。
そんなときに今一度、運用に問題が無いか、蓄積したデータをもとにPDCAが回せているか、などを確認してみてください。
「入力されているデータにばらつきがあり、データをうまく活用できていない。ルール決めが必要だ」など改善点が見えてくるかもしれません。
まとめ
いかがでしょうか
SFAを導入することで商談の進捗を見える化し標準化を促したり、情報の一元管理により業務効率化を実現します。
そんなSFAを効果的に活用、定着させるためにも、導入前に確認したいポイントについてご紹介させていただきました。
SFA導入の参考になれば幸いです。
SFAを導入することで商談の進捗を見える化し標準化を促したり、情報の一元管理により業務効率化を実現します。
そんなSFAを効果的に活用、定着させるためにも、導入前に確認したいポイントについてご紹介させていただきました。
SFA導入の参考になれば幸いです。